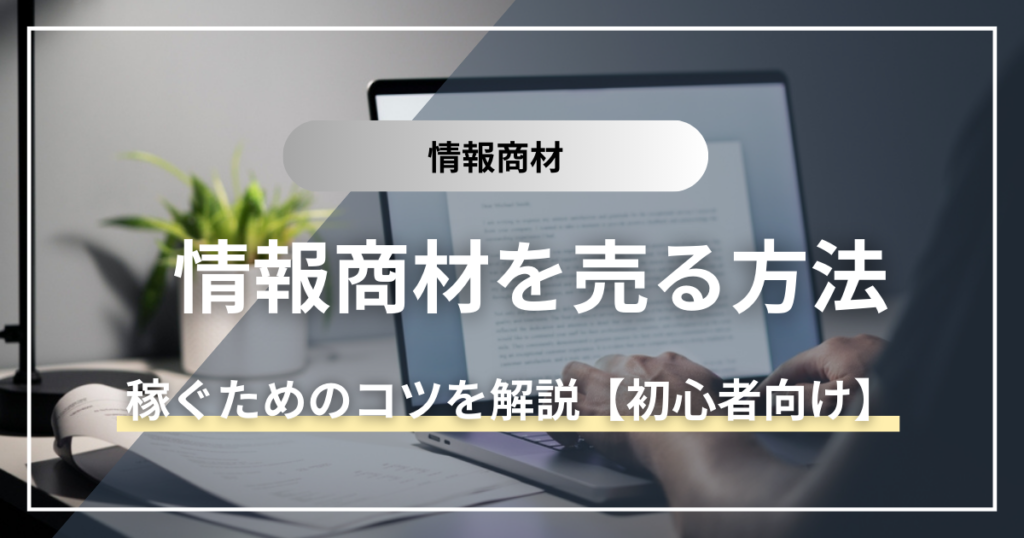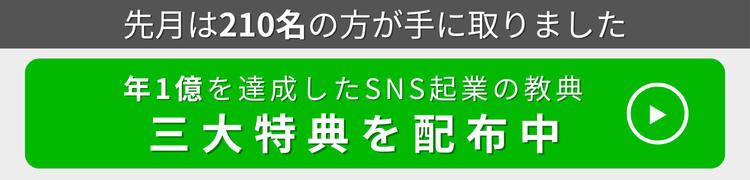「情報商材」と聞くと、怪しいイメージを持つ方も多いかもしれませんが、情報商材は正しく選べば知識を効率的に得られる有益な商品です。
しかし、誇大広告や信頼性の低い業者が存在するため、慎重に判断することが非常に重要になります。
この記事では、情報商材の定義から「怪しい」と言われる3つの理由を解説します。
また、安全な情報商材の選び方まで詳しく解説するので、キャリアアップや自由な生活を手に入れるための有益なノウハウを情報商材から得たい方はぜひ最後までご覧ください。
ではまず、情報商材の基本から見ていきましょう。
はじめに:情報商材とは?ビジネスモデルは?
「情報商材は危ない」というマイナスなイメージを持つ方は少なくありません。実際、情報商材の詐欺に関するニュースを目にしたことがある人もいることでしょう。
しかし、実際には情報商材はグレーなビジネス手法ではなく、正当な方法として広く使われています。
そもそも情報商材とは、主にインターネットを通じて知識やノウハウを販売するデジタルコンテンツを商品として販売するビジネスモデルを指します。
「コンテンツ販売」とも呼ばれており、電子書籍(PDF形式)や動画講座、音声ファイル、会員制サイトなどの形態で販売されています。
そのため、KindleやUdemyなどもコンテンツ販売の一種です。
情報商材で扱われる内容は多岐にわたります。
- ビジネススキル
- 投資知識
- 健康・美容法
- 恋愛テクニック など
情報商材では普通では知り得ないノウハウや情報を簡単に手に入れられるというメリットがありますが、デメリットもあります。
情報商材の品質にはばらつきがあり、すべての商品が信頼できるわけではありません。中には誇大広告を使用して消費者を惑わせるものもあります。購入を検討する際は、返金保証の有無や信頼性を確認することが大切です。
以上が、情報商材の概要でした。次に情報商材が危ないと言われる理由について論理的に解説します。
情報商材が「怪しい」「危険」と言われる3つの理由

情報商材が「怪しい」「危険」と考えられている理由としては、主に次の3つが挙げられます。
- 誇大広告で消費者を騙す業者が一定数存在する
- 無形商材のため価値が客観的に表しにくい
- 価格が高額である
ひとつずつ見ていきましょう。
理由①:誇大広告で消費者を騙す業者が一定数存在する
情報商材の多くは有益で、消費者ファーストのものばかりです。
しかし、一部の業者は、「簡単に大金を稼げる」「短期間で成功できる」といった誇大広告を使い、消費者を騙しています。
実際には、短期間で大きな成果を上げるのは極めて難しいにもかかわらず、過剰な宣伝文句で消費者を誘惑しようとするのです。
さらに、そのような情報商材の多くは発信内容の信憑性も低い傾向にあります。実績として「1ヶ月でフォロワー1万人増」と宣伝していても、それを証明するデータなどは提示しないなど、信憑性に欠ける事例が多く見られます。
コンテンツのジャンルで言えば、投資や副業などの情報商材では悪徳業者が比較的多いです。
「すべての情報商材=悪い」というわけではないにもかかわらず、このような一部の悪徳業者によって情報商材全体にネガティブな印象を抱いている消費者も少なくないことを覚えておきましょう。
理由②:無形商材のため価値が客観的に表しにくい
情報商材はデジタルコンテンツを販売します。つまり、無形の商品です。
デジタルコンテンツは一般的なモノのようにその価値が目に見えてわかるわけではありません。そのため「情報にお金を払う」という考えがまだ浸透していない日本では、無形商材に対する疑念を抱く人が少なくないのです。
一部の意識の高い人々は、無料で手に入る情報と有料の情報の違いを理解していますが、多くの消費者にとっては「見えないものにお金を払う」ということに未だに抵抗感を感じます。
理由③:価格が高額である
情報商材は無形の商品であるにもかかわらず、価格が非常に高額であることも「怪しい」と思われる原因の一つです。
情報商材の相場は数万円から数十万円に及ぶことが多く、購入者がその内容に対して適切な価値を感じられないと「詐欺に遭った」と思い込む可能性があります。
特に、期待した成果が得られなかった場合には経済的なダメージだけでなく、心理的ダメージも大きくなるからです。
さらに、デジタル商品の性質上、一度購入すると返金が難しいケースが多いです。
販売ページでは「返金保証」と謳っている場合もありますが、その条件が厳しく、実際には返金を受けられないことも少なくありません。
このような状況が情報商材に対する不信感を増幅させ、「高額なだけで価値がない」と感じる消費者が増える原因となっているのです。
しかし、何度も述べている通り、情報商材のなかには有益なものもたくさんあります。つぎでは「安全な情報商材の見分け方」について解説します。
安全な情報商材ビジネスに共通する3つの特徴

信頼できる情報商材ビジネスには、いくつかの共通点があります。ここでは、特に重要な3つの特徴を紹介します。
- 販売者の実績や個人情報が公開されている
- 具体的で現実的な内容・ノウハウを公開している
- 返金保証などの顧客サポートがついている
それぞれ見ていきましょう。
特徴①:販売者の実績や個人情報が公開されている
安全な情報商材の特徴の1つ目は、販売者の実績や個人情報が公開されていることです。
特に、ビジネスや投資関連の情報商材では、販売者自身が実際にその分野で成功を収めているかどうかが信頼性の指標となります。
例えば、X運用を題材にした情報商材を購入する際には、その販売者が「どうやってXのフォロワーを増やしたか」「どれくらいのフォロワーを抱えているか」などのノウハウや実績を必ず確認しましょう。
また、販売者が業界で認知された専門家であるかどうか、関連する資格を持っているかなども重要なポイントです。
このように販売者の情報がオープンにされている商材は、信頼性が高く、安心して活用できるものと言えます。
特徴②:具体的で現実的な内容・ノウハウを公開している
安全な情報商材は、具体的で現実的な内容やノウハウを公開しています。
裏を返せば「誰でも寝ているだけで稼げる」といった、非現実的な宣伝をする情報商材は悪質なものの可能性が高いです。
どんなビジネスをするにしても、成功するためにはある程度の努力が必要だからです。しかし、その努力の方向性を正しく定めることができれば、最小限の労力で成功することが可能です。
例えば、成功へのステップを具体的に解説し、努力の方向性を明確にしている商材は、安全で信頼できます。
「1週間で1000万円稼ぐ」などの耳当たりの良い目標ではなく、「6ヶ月間で副業収入を月10万円増やす」といった現実的な目標を提示する商材のほうが信頼性が高いです。
また、リスクや課題などのネガティブな面についても正直に言及し、それに対する対処法を含めた説明がされていると更に信用できるでしょう。
特徴③:返金保証などの顧客サポートがついている
信頼できる情報商材ビジネスには、返金保証や充実した顧客サポートがついています。
特に「30日間の全額返金保証」など、一定期間内であればリスクなく商材を試せる仕組みがあれば、販売者の誠実さが伺えるでしょう。
「購入後のサポート体制が整っているか?」これも重要な要素のひとつです。
例えば、購入者の質問に対する迅速な対応や商材の内容に基づいたアップデートの提供、個別コンサルの無料実施といった特典が充実していると費用対効果の高い情報商材だと言えます。
良質な情報商材を選ぶためには、商材自体の魅力はもちろんのこと、それ以外の面でも内容が充実しているか確認することが大切です。
情報商材の作り方・売り方
情報商材で稼ぐとき、まずは情報商材の作り方が気になるかと思います。
そもそも情報商材で稼ぐ場合、商品を購入してくれるお客様がどのような情報を欲しがっているのか、競合と違ってどんなものを求めているのかを明確に洗い出す必要があります。
また、その情報商材を手売りするわけにもいきません。情報商材で稼ぐのであれば、ある程度ファネルを構築し、自動化を進めることで大きな収益が見込めます。
そのためにも、情報商材の作り方・売り方はしっかりと学んでおきましょう。情報商材の作り方売り方は以下の記事にて紹介しています。
参考 情報商材の作り方を紹介!
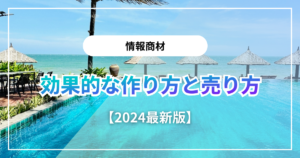
情報商材はどこで売る?
情報商材で収益化を始める際、どのプラットフォームを使うべきかは最も悩むところかと思います。
実際のところどのプラットフォームを使用しても間違いではありません。ただし、自分がどのような情報を売るかによって使い勝手の良いプラットフォームは異なってきます。そのため、情報商材を販売する際はプラットフォームの見極めは大切です。
以下の記事では情報商材をどのプラットフォームで販売すべきかについてまとめています。

まとめ:情報商材ビジネスで安全に自由な暮らしを手に入れよう!
今回は、情報商材について解説しました。
世間では「情報商材=怪しい」と言われることもありますが、それは一部の悪徳業者が作り上げた評価です。
実際には良質なコンテンツを発信している情報商材もたくさんあります。
そのため、有益な情報商材を購入するためには、その良し悪しを見極めるユーザー側の目利き力が要求されます。
情報商材は、正しい選び方をすれば、自由な暮らしを手に入れるための有力な手段です。
信頼できる販売者が提供する具体的で現実的な内容の商材を選び、効率的に知識やスキルをインプットしましょう。
情報商材をうまく活用し、最短距離で目標達成を目指していただければ幸いです。